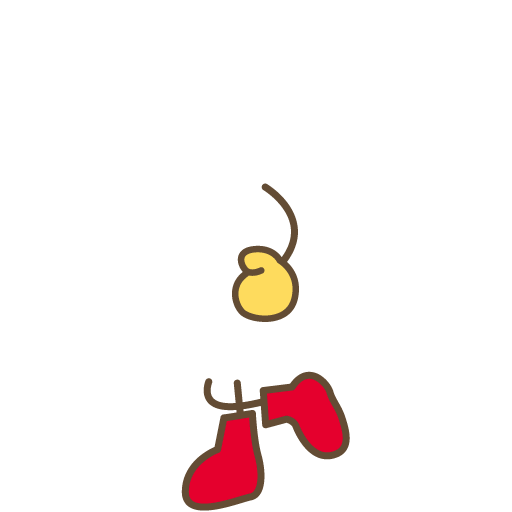イヌマキ マキ科の常緑針葉高木
関東以西から中国に自生しています。真木(まき)とされるスギやコウヤマキに劣るということでイヌマキと呼ばれます。防風、防火樹として優れ、防風林や生垣として使用されています。雌雄異株で雌株には秋に緑色の種子の基部の花托という部分が赤く肥大した、緑と赤の串団子のような食べられる実がなります。ただし、緑の種子部分には毒があります。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
オオシマザクラ バラ科の落葉高木
伊豆大島や伊豆諸島、伊豆半島に自生している白花のサクラです。このサクラを親とする品種が多数存在し、ソメイヨシノ、カンザン、カワヅザクラなどがよく知られています。古くから燃料として利用されタキギザクラの別名があります。また、葉の香りが良く、塩漬けにしたものが桜餅の葉に使われモチザクラとも呼ばれています。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
オキナグサ キンポウゲ科の多年草
日本では北海道を除く各地、中国、朝鮮半島に自生します。4月から5月に赤紫色の花を咲かせた後にできる綿毛のような種子が白髪に見立てられて翁草と呼ばれるようです。自生地の破壊や園芸採集の乱獲により減少して絶滅危惧種とされています。全草に毒があり漢方に利用されます。園芸には色数多いセイヨウオキナグサがお勧めです。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
カキノキ カキノキ科の落葉高木
中国原産とも日本自生とする説もあります。赤き実や赤木が語源とされています。多数の品種が各地に存在するうえに品種改良が進み1,000を超えるとされています。甘柿と渋柿に分けられ、甘柿は渋柿の突然変異とされています。渋柿は干し柿にしたりアルコール脱渋したりして食します。また、渋柿塗りの和傘や団扇、柿の葉寿司、高級家具材に使用されます。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
カラタネオガタマ モクレン科の常緑高木
日本にもアメノウズメが天岩戸の前で手に持って踊ったとされるオガタマノキが存在しますが、本種は中国原産で江戸時代に伝わりました。神に供える唐(カラ)から来た招魂(オガタマ)の木と呼ばれ寺社に多く植えられました。バナナの香りが特色でバナナノキと呼ばれることもあります。美しい花を観賞用とする以外の用途はありません。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
キエビネ ラン科の多年草
紀伊半島から西の日本、中国に自生しています。エビネの仲間で鮮やかな黄色の花をつけるのは本種だけです。西日本にエビネと自然に交雑したタカネ・ヒゴ・サツマエビネなどが存在します。森林伐採や園芸採取による乱獲で減少して絶滅危惧種とされています。エビネは前年の球根を含む古い球根の連なりが海老の背中に似ているところが語源です。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
クワ クワ科の落葉高木
中国から朝鮮半島が原産地です。絹糸をとる養蚕が伝えられると同時に日本に入ってきました。カイコが「食う葉」ないしは蚕葉(こは)が転じたのが語源とされています。日本在来のヤマグワがありますが、餌として劣り、カイコの成長が悪いので霜害を受けたときにクワの代用品とされます。クワの実は食べることができ、マルベリーと呼ばれます。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
ザクロ ミソハギ科の落葉高木
原産地がトルコやイランとする説、北アフリカとする説などがありはっきりしていません。トルコから中東にかけての地域ではポピュラーな果物で色々な色のものがあります。中国経由で伝わり中国名石榴(ジャクル)が語源とされています。赤い多汁の種皮をもった種子がたくさん入っていることから世界的に子孫繁栄のシンボルとされています。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
シバザクラ ハナシノブ科の多年草
北アメリカ原産の植物です。4月から5月にかけてサクラに似たピンクや白、白地にピンクの筋が入ったものなどの花を咲かせます。葉が小さく茎から次々と根を下ろして芝のように這う姿から芝桜(シバザクラ)と名付けられました。しかし踏みつけに弱いので芝生のように立ち入れません。日本各地にこれを観光の目玉とする施設が多数あります。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
シモバシラ シソ科の多年草
日本固有の植物で関東から西の森林内や渓谷沿いに自生します。9月から10月に穂状に白い花を咲かせます。軸に万遍なくつけるのではなく片側に偏った花のつけ方をする変わった植物です。冬に枯れた茎の地際の部分の道管内の水が凍って、割れ目から噴出した氷が霜柱に似ることから名付けられました。氷点下の早朝に見られます。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
タイリョウザクラ バラ科の落葉高木
熱海市の育種家がオオシマザクラとカンザクラの交配から選抜したサクラです。色が大漁の桜鯛に似るところから名付けられました。日本国内外の桜の名所づくりをしている「日本花の会」の名所づくり推奨品種の一つで、三陸被災地の支援として宮城県女川町に贈られました。大和市のボランティア団体がアジサイを贈った縁で大和市にも贈られました。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
ナンテン メギ科の常緑低木
原産地は中国からインドにかけてです。江戸時代に伝わって、茨城県から西の地域で野生化しました。中国名の南天燭や南天竹を語源とします。難を転じるに通じ、縁起の良い木として正月飾りの鉢物や厠の近くに植えられるなどのほか、料理のあしらいにも使われます。材は黄色で、太るのに年数を要しますが寺院や茶室の高級建材として使われます。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
モッコク モッコク科の常緑高木
関東以西からインドに自生しています。江戸五木の一つとされ、生育が穏やかで姿が崩れなく高級感があるところから庭木の王様とも呼ばれ、高く造園界では評価されています。花に芳香がありセッコク(石斛)の香りに似ていることからモッコク(木斛)と呼ばれるようになったそうです。材は赤褐色で床柱などの建材や櫛などの工芸品に使われます。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)
ワレモコウ バラ科の多年草
北海道から西、中国、朝鮮半島、シベリアに自生しています。7月から10月に枝先に団子のように暗赤紫色の小さな花を密集させて咲かせます。吾もまた紅なり(吾亦紅)と自らが言ったとかいう日本昔ばなしのような語源説があります。香りもないのに(吾木香)という説もあり、はっきりしません。若葉は食べられますし、根は生薬になるそうです。(解説文:グリーンアップセンター みどりの相談員 松尾宏一氏)