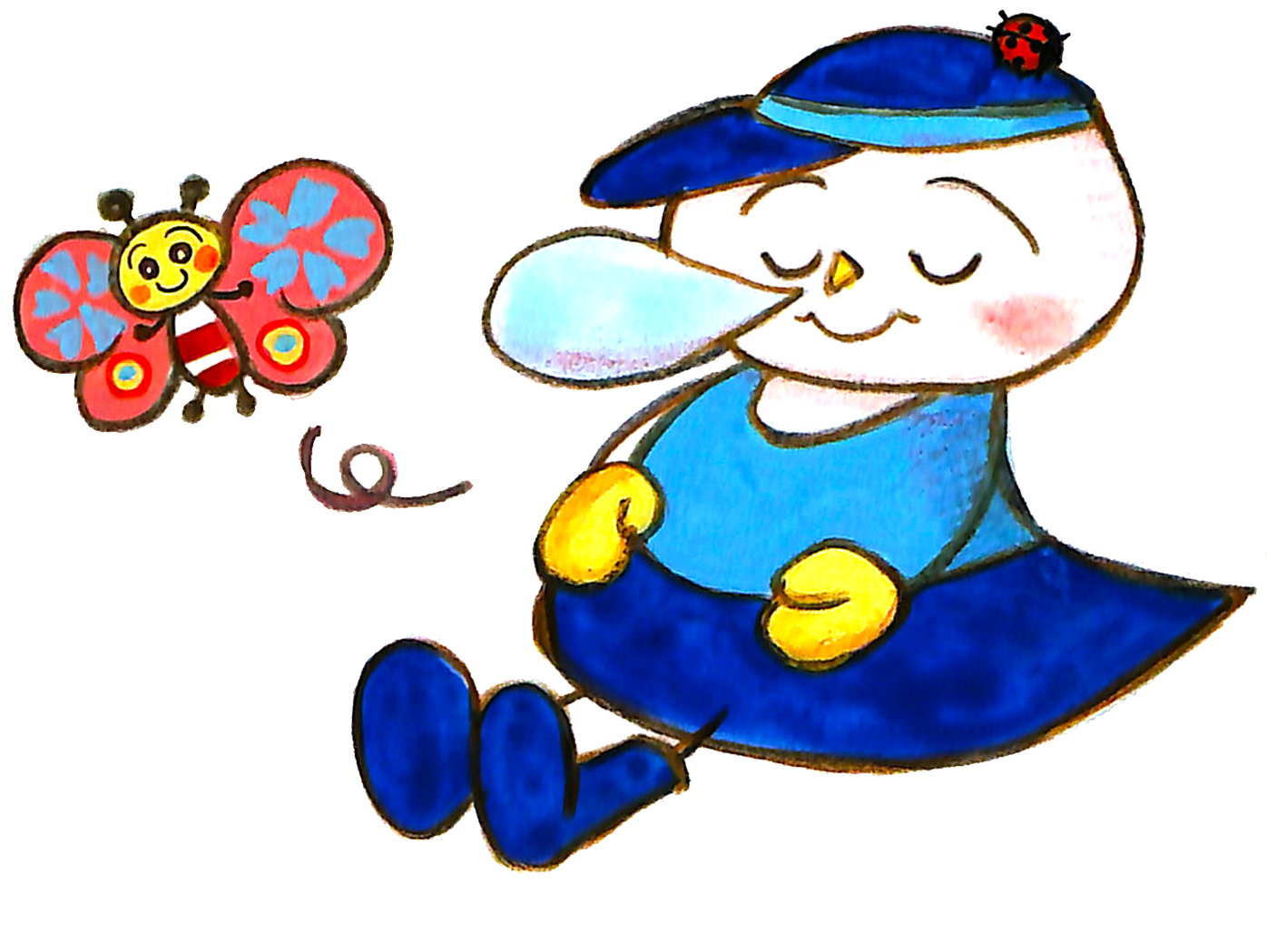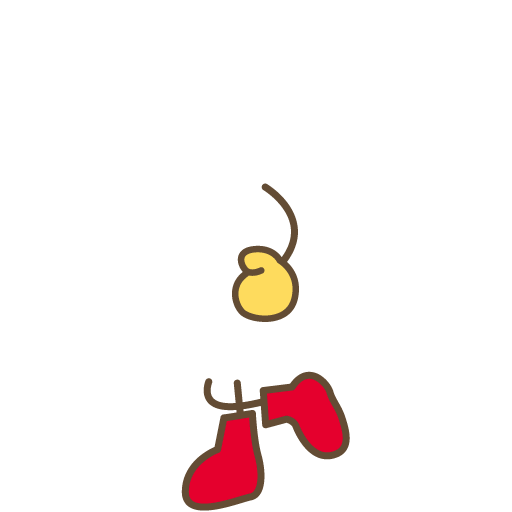1/23(金)文化財防火デー消防訓練
1月23日(金)に、文化財防火デーにちなんだ消防訓練を実施します。
昭和24年1月26日に、世界最古の木造建築物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことから、1月26日は文化財防火デーに制定されています。当園では毎年これに近い日に、消防訓練を実施しています。
当日は訓練中も入園が可能で、最初に行う放水訓練をご見学いただけます。ただし、古民家内の見学はできません。
文化財保護のため、来園する皆様におかれましては、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
昭和24年1月26日に、世界最古の木造建築物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことから、1月26日は文化財防火デーに制定されています。当園では毎年これに近い日に、消防訓練を実施しています。
当日は訓練中も入園が可能で、最初に行う放水訓練をご見学いただけます。ただし、古民家内の見学はできません。
文化財保護のため、来園する皆様におかれましては、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
郷土民家園の植物豆知識「春の七草」
春の七草
セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロの七種類の野草のことです。それぞれ消化の促進や整腸などの薬効があり、お正月のご馳走で疲れた胃腸をいたわるため、一月七日の七草粥のときに古くから食べられてきました。
・セリ(芹)セリ科
セリ科の多年草で独特の香りがします。名前の由来は、若葉が競り合うように成長することから来ているそうです。なお、セリは綺麗な水辺に生えていることもありますが、姿がそっくりなドクゼリ(名前の通り毒があります)の場合がありますので、専門知識がない場合は、採集したものを食べるのは避けましょう。
・ナズナ(薺)アブラナ科
アブラナ科の越年草(二年草)で別名ペンペングサといいます。名前の由来は諸説ありますが、一説には撫でたいほど小さくてかわいい花という意味の撫で菜から変化したといわれています。七草粥や薬として食用されるだけでなく、おもちゃとしても使われるなど古くから人々に親しまれてきた植物の一つです。
・ゴギョウ(御形)キク科
キク科の越年草で、現在は一般的にはハハコグサと呼ばれています。古い言い方であるゴギョウは、ひな祭りの際、厄除けの為に御形といわれる人形(ひとがた)を川に流した古い風習が関係しているといわれています。また、草餅にも使われて、江戸(あるいは明治)時代以前まではヨモギを使った草餅よりも、こちらの方が一般的だったそうです。
・ハコベラ(繁縷)ナデシコ科
現在一般的にハコベと呼ばれている植物で、コハコべやミドリハコベなどの総称としても使われます。古くより食用や薬用にされ、特に塩と混ぜたものはハコベ塩として、歯磨き粉や歯槽膿漏の薬に使われていました。
・ホトケノザ(仏の座)キク科
現在コオニタビラコと呼ばれているキク科の越年草です(ホトケノザは現在シソ科の別の植物の標準和名となっています。こちらは食用ではないので注意が必要です)。名前の由来は、葉のつき方が仏さまの円座に似ているから。ありがたい姿の植物なのですね。
・スズナ(菘)アブラナ科
アブラナ科の越年草で、現在のカブのことです。名前の由来は、根が鈴のように見えることから、鈴のような根がある菜でスズナとなったそうです。カブは、普段食用する根の部分と葉の部分で含まれる栄養が異なります。七草粥では葉と根の両方を入れて無駄なく栄養を摂ります。
・スズシロ(蘿蔔)アブラナ科
アブラナ科の越年草で、現在のダイコンのことです。名前の由来は、根の部分が白いことから、清く白いと書いて「清白(すずしろ)」から来ているそうです。スズシロもスズナと同じように葉と根共に栄養が豊富で、特に根の部分は、消化酵素を多く含んでいるため、お正月のご馳走で疲れた胃には最適です。
セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロの七種類の野草のことです。それぞれ消化の促進や整腸などの薬効があり、お正月のご馳走で疲れた胃腸をいたわるため、一月七日の七草粥のときに古くから食べられてきました。
・セリ(芹)セリ科
セリ科の多年草で独特の香りがします。名前の由来は、若葉が競り合うように成長することから来ているそうです。なお、セリは綺麗な水辺に生えていることもありますが、姿がそっくりなドクゼリ(名前の通り毒があります)の場合がありますので、専門知識がない場合は、採集したものを食べるのは避けましょう。
・ナズナ(薺)アブラナ科
アブラナ科の越年草(二年草)で別名ペンペングサといいます。名前の由来は諸説ありますが、一説には撫でたいほど小さくてかわいい花という意味の撫で菜から変化したといわれています。七草粥や薬として食用されるだけでなく、おもちゃとしても使われるなど古くから人々に親しまれてきた植物の一つです。
・ゴギョウ(御形)キク科
キク科の越年草で、現在は一般的にはハハコグサと呼ばれています。古い言い方であるゴギョウは、ひな祭りの際、厄除けの為に御形といわれる人形(ひとがた)を川に流した古い風習が関係しているといわれています。また、草餅にも使われて、江戸(あるいは明治)時代以前まではヨモギを使った草餅よりも、こちらの方が一般的だったそうです。
・ハコベラ(繁縷)ナデシコ科
現在一般的にハコベと呼ばれている植物で、コハコべやミドリハコベなどの総称としても使われます。古くより食用や薬用にされ、特に塩と混ぜたものはハコベ塩として、歯磨き粉や歯槽膿漏の薬に使われていました。
・ホトケノザ(仏の座)キク科
現在コオニタビラコと呼ばれているキク科の越年草です(ホトケノザは現在シソ科の別の植物の標準和名となっています。こちらは食用ではないので注意が必要です)。名前の由来は、葉のつき方が仏さまの円座に似ているから。ありがたい姿の植物なのですね。
・スズナ(菘)アブラナ科
アブラナ科の越年草で、現在のカブのことです。名前の由来は、根が鈴のように見えることから、鈴のような根がある菜でスズナとなったそうです。カブは、普段食用する根の部分と葉の部分で含まれる栄養が異なります。七草粥では葉と根の両方を入れて無駄なく栄養を摂ります。
・スズシロ(蘿蔔)アブラナ科
アブラナ科の越年草で、現在のダイコンのことです。名前の由来は、根の部分が白いことから、清く白いと書いて「清白(すずしろ)」から来ているそうです。スズシロもスズナと同じように葉と根共に栄養が豊富で、特に根の部分は、消化酵素を多く含んでいるため、お正月のご馳走で疲れた胃には最適です。